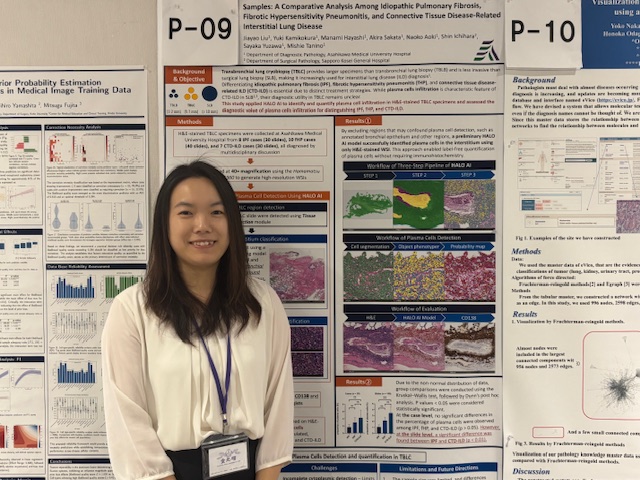当部の湯澤先生が共著した論文の「Successful Identification and Treatment of Cancer of Unknown Primary Originating From Gastric Cancer Using Comprehensive Genomic Profiling and Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: A Case Report.」がCancer Rep (Hoboken) (IF= 1.9) にアクセプトされました。
「Cancer of Unknown Primary Originating」は「原発不明癌」という意味です。
「Primary」は一般的には日本語で「主要な」「第一の」などの意味で知られていますが、医療においては「病気の原発 (※原子力発電の略ではないです)」の意味合いがあります。
このように、医学英語として用いると意外な意味を示す言葉は結構あります。
例えば「Viable」は、「実行可能な」などの意味が有名ですが、医療では「細胞・組織として生きている」という意味になり、抗癌剤で倒しきれていない癌細胞を「Viableな癌細胞」と称したりします。
また、コードや点滴チューブなどが何かに引っかかって、捻れて危ない状態を「キンキンしている」と言います。
私は初期研修医の時、患者さんをストレッチャーにお乗せする際に上級医が「点滴、キンキンしてる!」と言っていて、咄嗟のことでどっかの方言が出とるわwと思っていたのですが、「Kinking」と言う立派な英単語でした。
無知がPrimaryの恥ずかしい思い出で、今でもViableです。