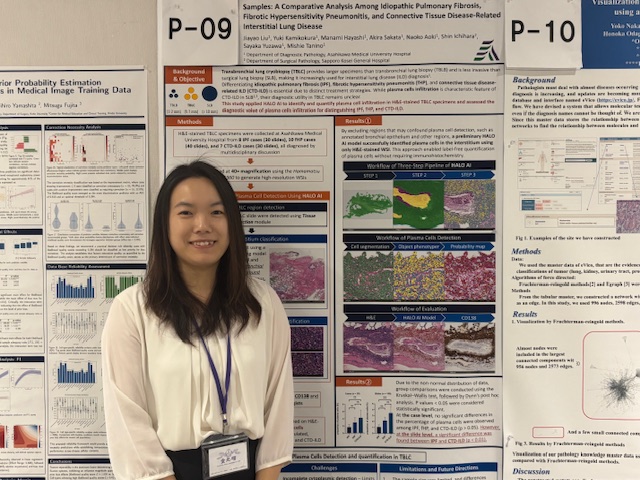当部の谷野先生、林先生、劉先生、本学学生の江藤さんが札幌の北広島クラッセホテルで開催の第20回北海道病理夏の学校 〜学生・研修医のための病理学セミナー〜に参加しました。
世話人は北海道大学の田中伸哉先生で、北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学の 学部学生、研修医、教官など合わせて51名が参加しました。
東京大学医学部人体病理・病理診断学教室の牛久哲男先生が特別講演され、恒例の臨床病理検討会のほか、学生セッション、専攻医セッション、病理診断、研究に関わる教育講演と、2日間に渡って盛りだくさんの内容でした。
18時半からの懇親会は2次会、3次会と続き、学生・医師が混在して様々な話で盛り上がりました。
学生セッションでは旭川医大5年生の江藤朋憲さんが病理学会、専攻医セッションでは病理部の林真奈実先生が自身の専攻医時代の経験から現在までの話をしました。
谷野先生が座長を行いました。
医局員の秋田谷先生は常呂厚生病院から参加し、病理部大学院生の劉先生も参加しました。
とても充実した楽しい時間を過ごしました。
「学校」と銘打っている通り、病理に興味のある学生や若手医師のために毎年開催されている会で、更に興味を深めてもらうために、現役病理医が様々な企画を御用意しています。
自分が好きなことを仕事にすると、それが好きじゃなくなった時、仕事が続けられなくなります。
また、仕事にしたせいで、それが好きじゃなくなってしまうこともあります。
ですが、自分の仕事に興味を持たないと、長くは続けられません。
「好き」や「興味がある」などの様々な所見を読み取り、「自分は本当に病理を仕事として続けられるのか」を自分の目で見極めるのが、病理初学者が初めて自分一人で下す診断だったりします。
「病理診断書なんて書けねぇ」という人でも、私達がお手本書きますから、気になった人は来年の「病理愛の、学校」に是非参加してみて下さい。