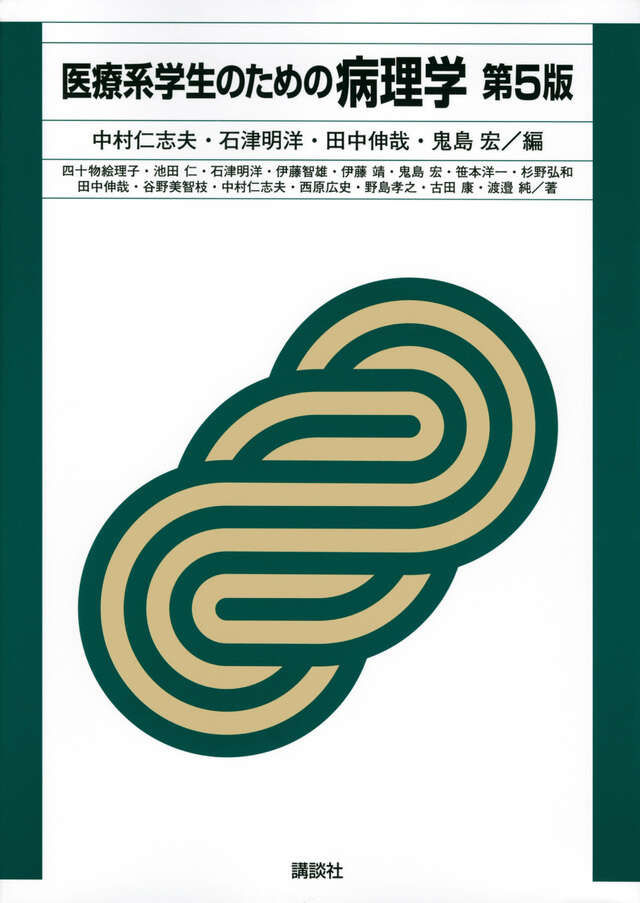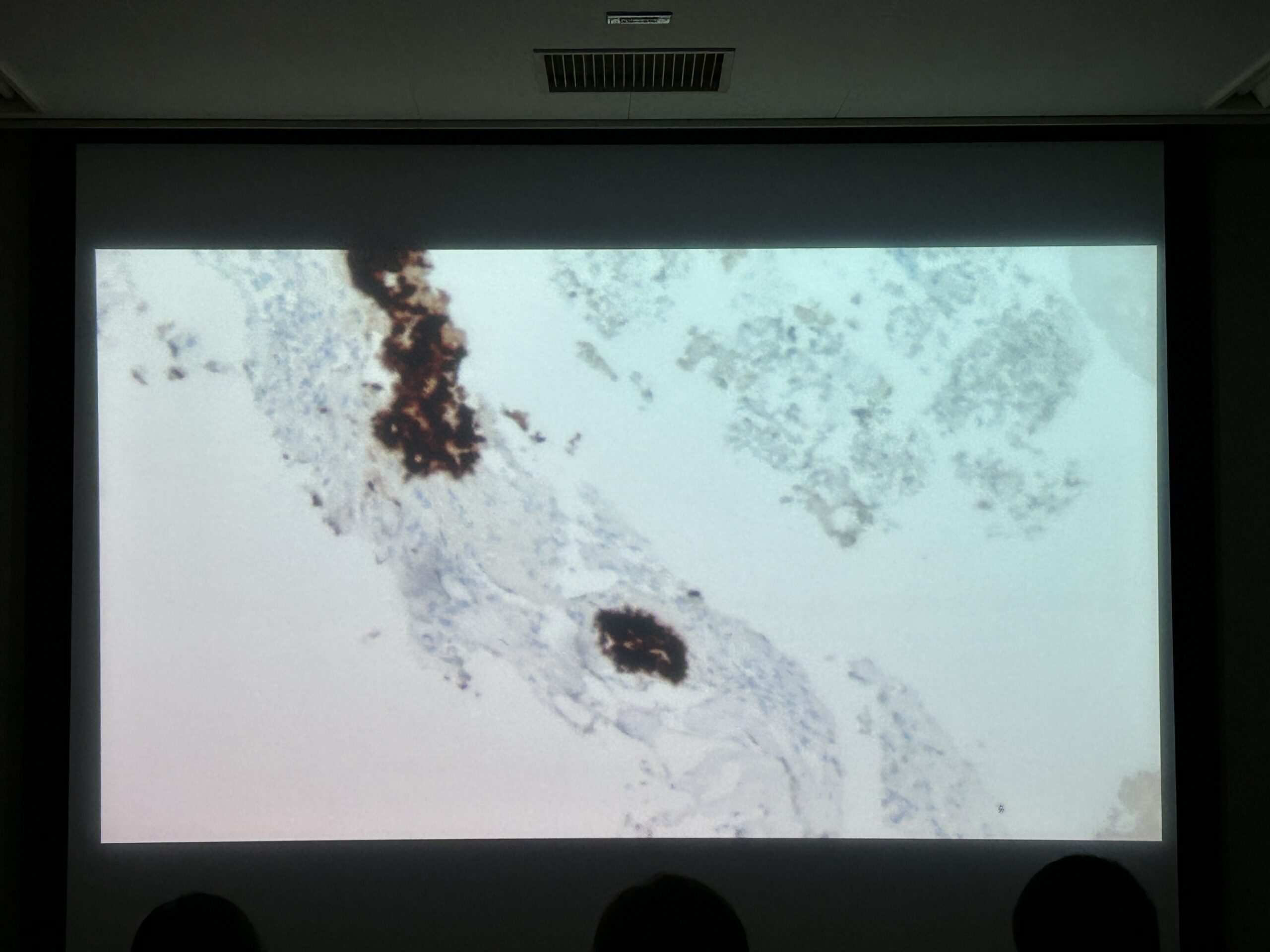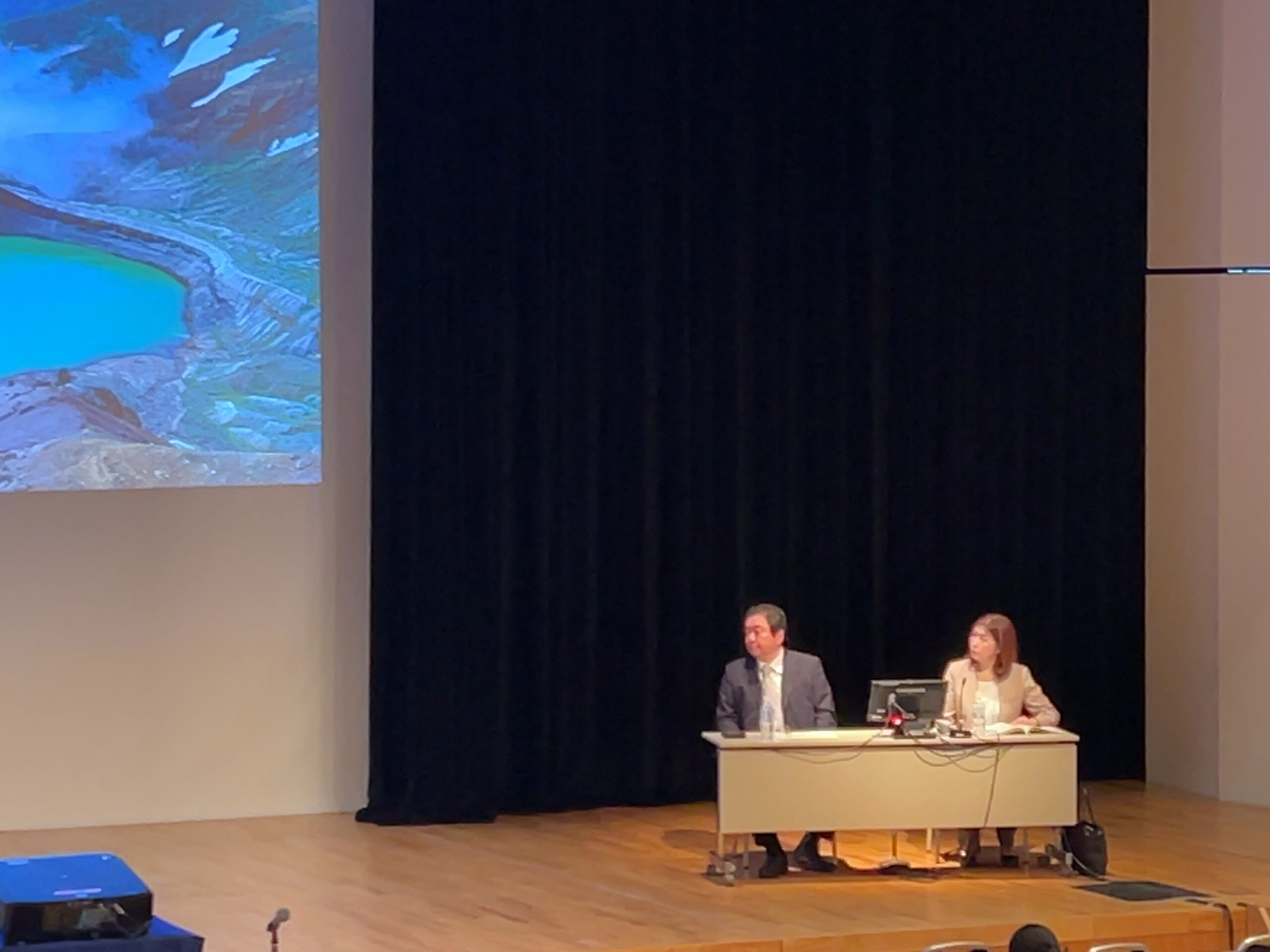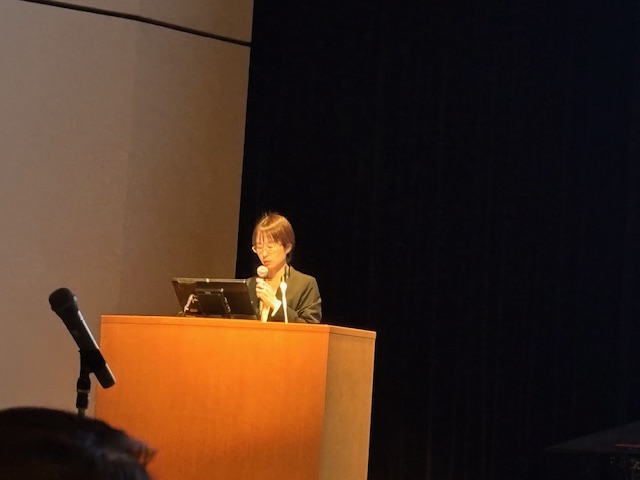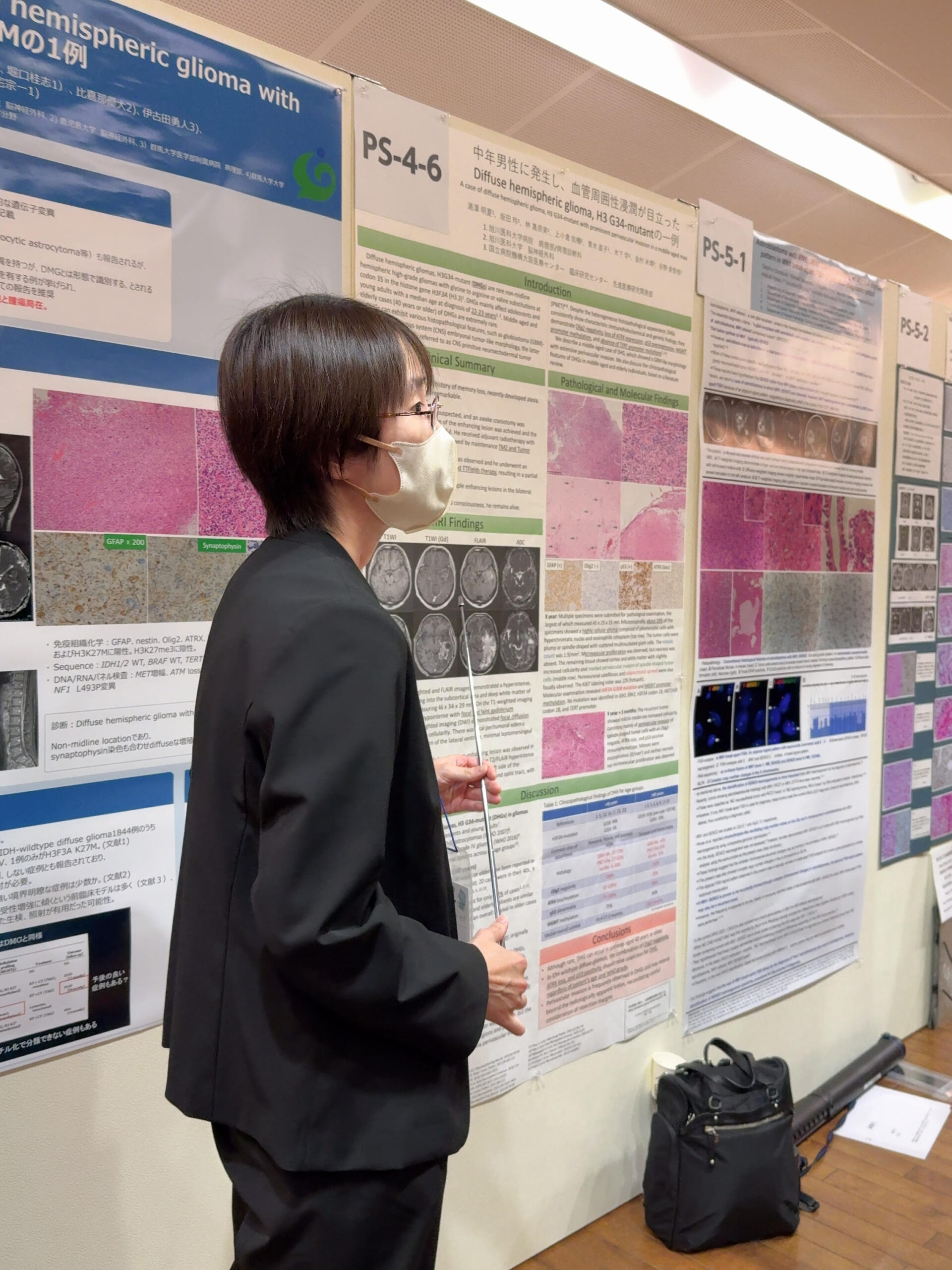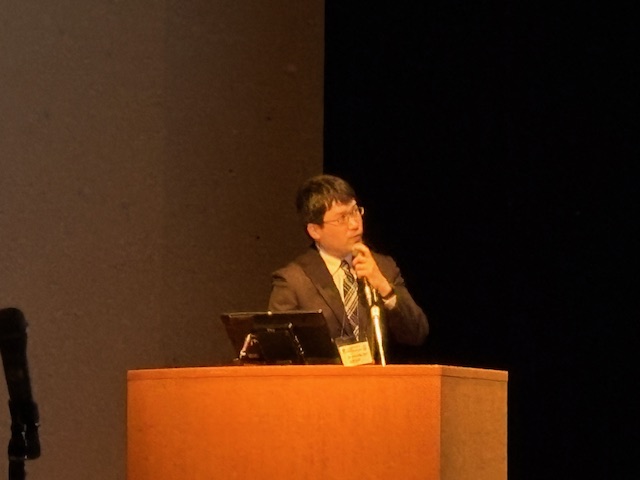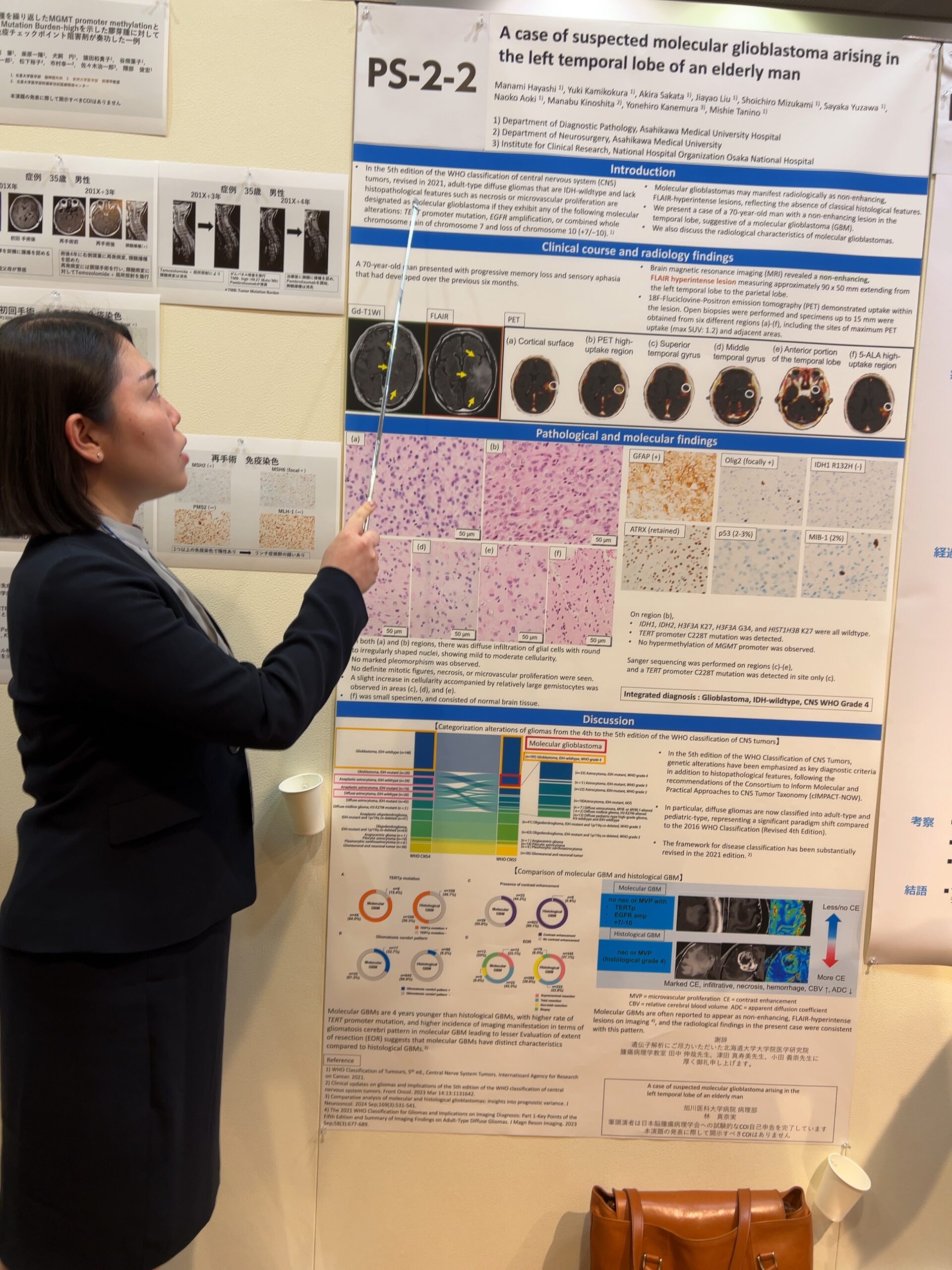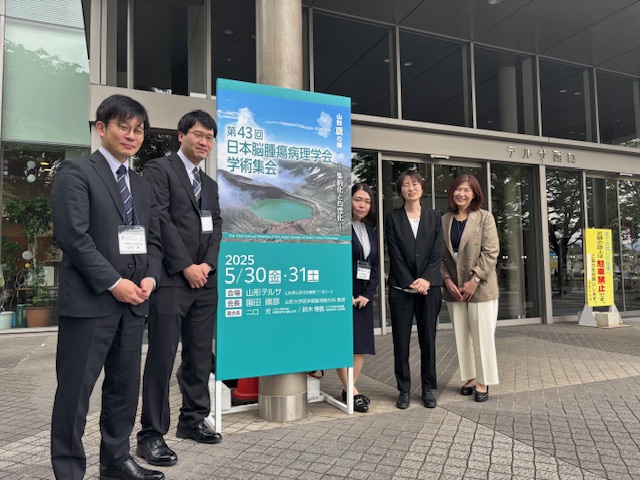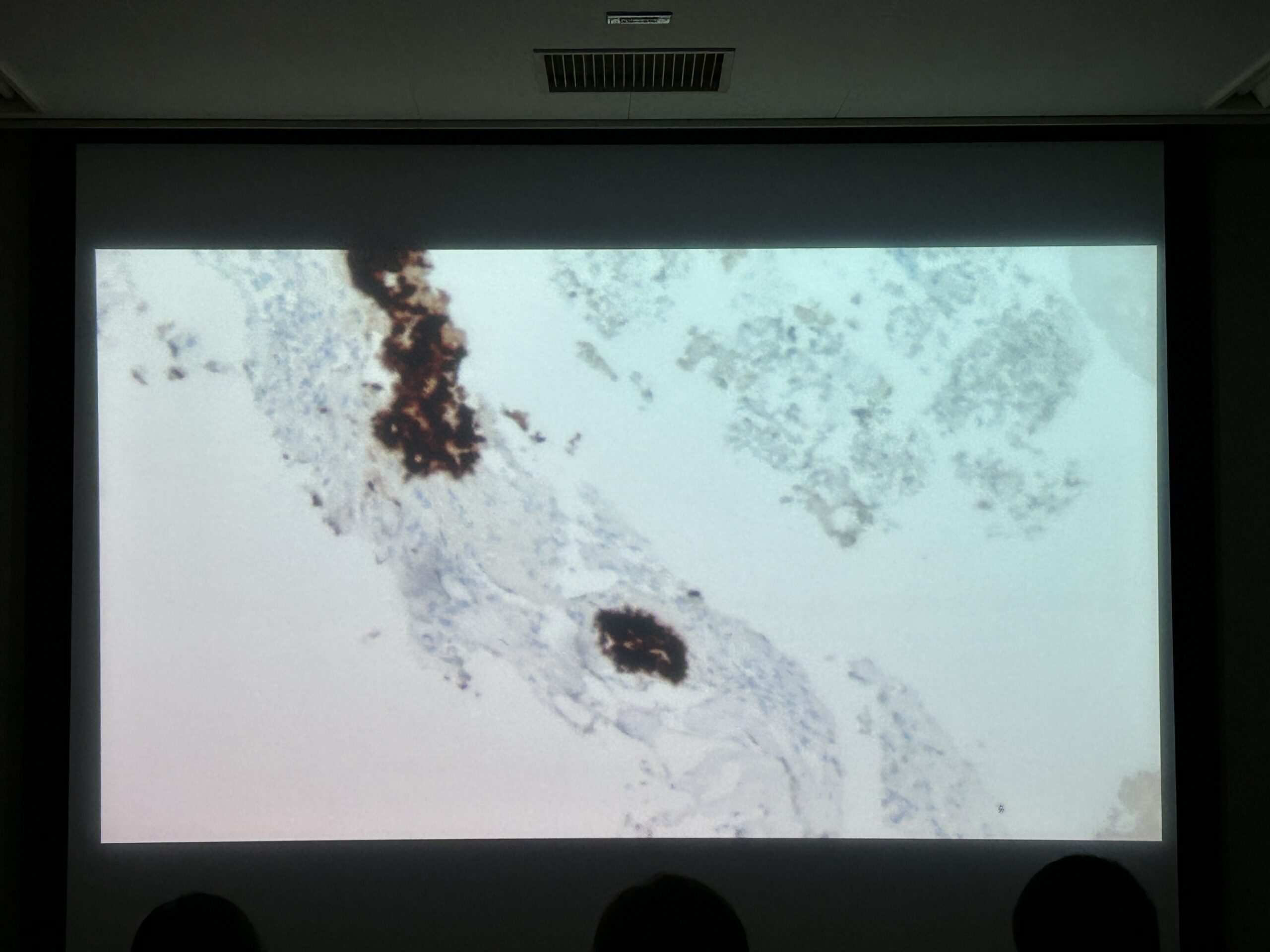
当院泌尿器科との合同カンファレンスにて、当部の谷野先生、林先生が症例提示を行いました。
今回は臨床医的に予想外な診断だった症例が取り上げられました。
実際に患者さんを入念に診察して、手術をした臨床の先生の実感とは異なる病理診断だったため、臨床と病理、互いの観点から盛んに意見が交わされました。
決して臨床の先生を咎める訳ではないのですが、どうしても臨床診断と、実際の病理学的診断に乖離が生じることはあり得ます。
医学には、「後医は名医」という言葉があり、後から情報がたくさんある状態で診察する医師の方が、最初に診た医師より正確な診断ができるのは当たり前なのです。
なので、むやみやたらに同業者を批判してはいけないことになっています。
これは医学以外にも通用する考え方で、自分と同じことができない人は、本当に自分と同じ条件下でやっているのかと考える必要があります。
自分ができたことができない人は努力が足りないからだ、と決めつけるより、その人が何に苦戦しているのかを思いやる方がとっても建設的です。
私もパワハラやモラハラは大嫌いですが、知らず知らずの内に物事を決めつけてかかって、それが不適切行為になっているかもしれないと、日頃から意識しています。
柔軟な視点は、剛情なハラスメントを、よく制すのです。