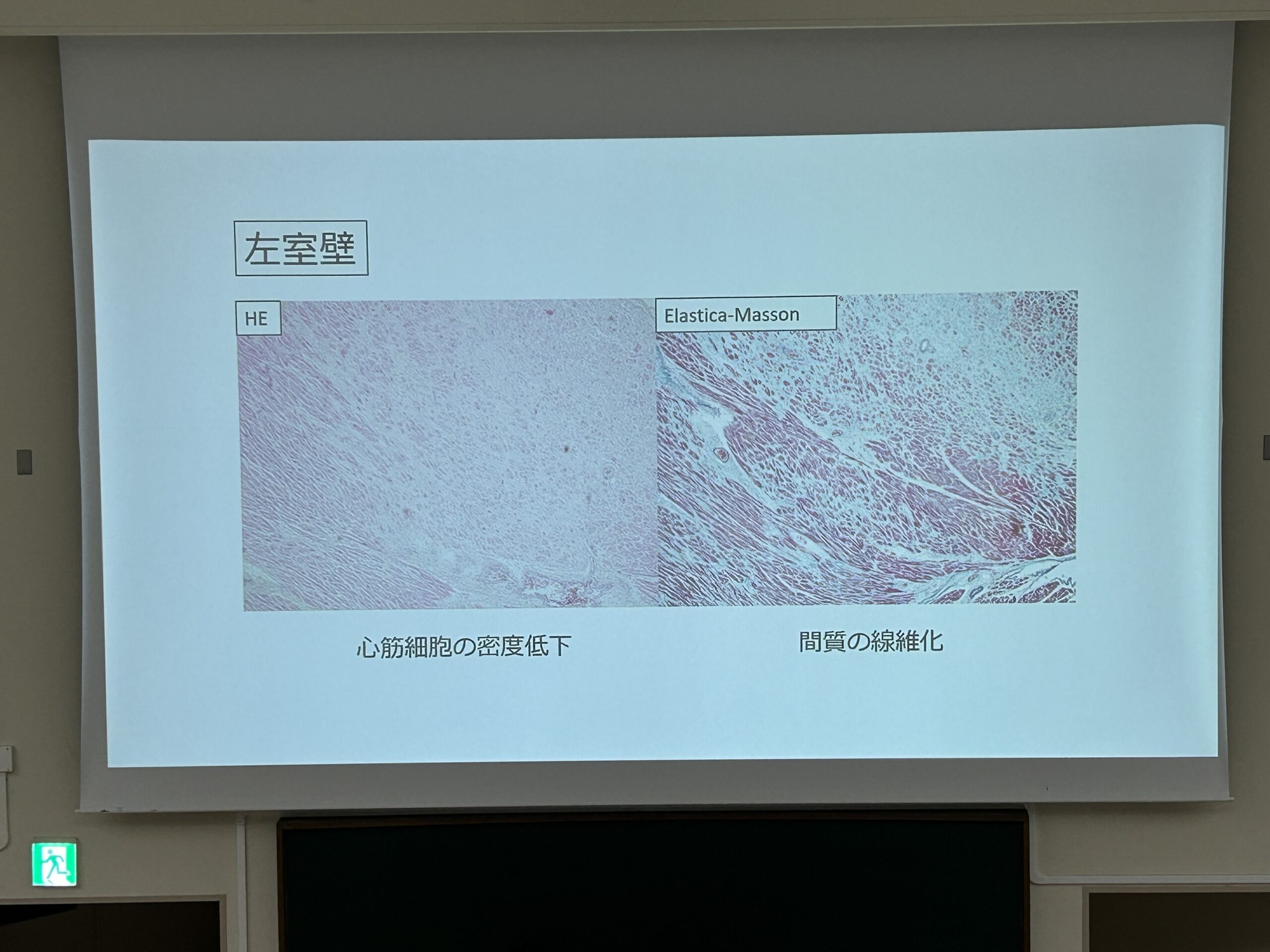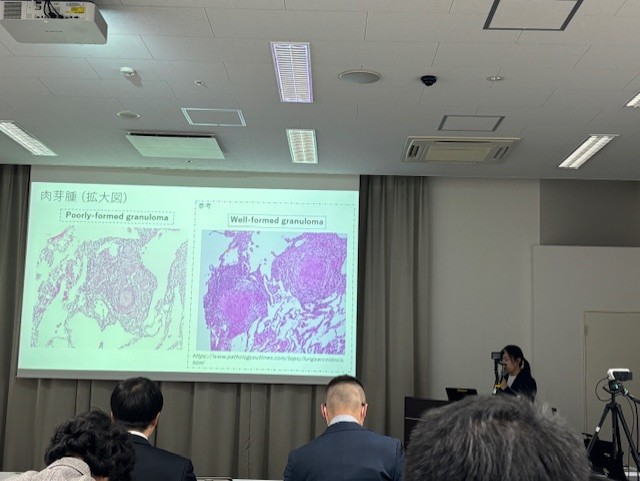岡山大学病院 病理診断科・病理部 教授の柳井広之先生が当部で特別講演をして下さりました。
谷野先生が閉幕の御挨拶を務めた、別会場で開催されるセミナーのために旭川にお越しになり、その途中に当院にお立ち寄り下さりました。
講演は「小児・AYA世代の卵巣腫瘍」という題で、組織標本を実際に顕微鏡で見ながらの実践的な内容で、とても勉強になりました。
柳井先生、お忙しい中、誠にありがとう御座いました。
「AYA世代」とは「Adolescent &Young Adult世代」、日本語で「思春期・若年成人世代」という意味です。
若年者の癌は本当に診断が難しく、病理像以外の情報も重要になってくるので、どういう状況でその検体が提出されたのかまでを詳細にお教えいただけて、リアリティーがあり、伝わってくるものが多く、とても勉強になりました。
柳井先生が築き上げられた教えを我々次世代に伝えて下さることで、病気に苦しむより多くの次世代の患者さんを救うことができます。
団塊の世代にも、ゆとり世代にも、Z世代にも、医療は世代を超えて新世代に受け継がれていくのです。